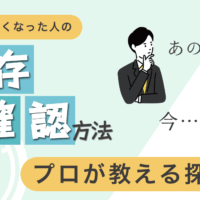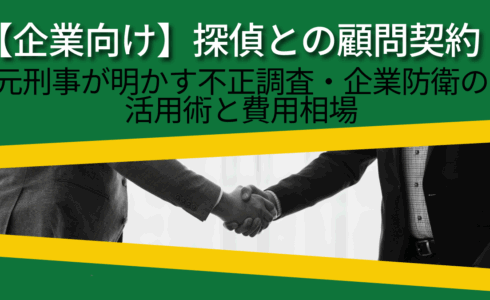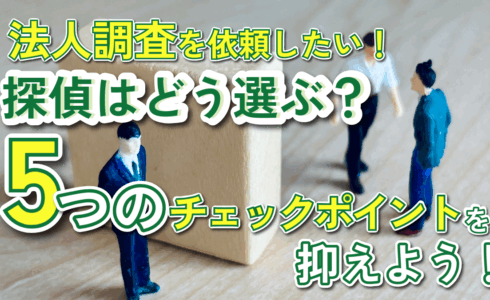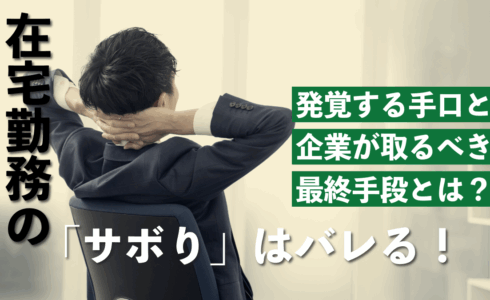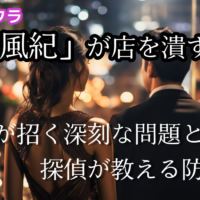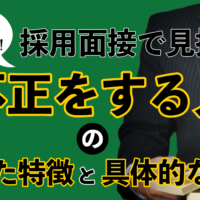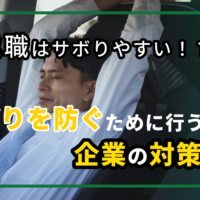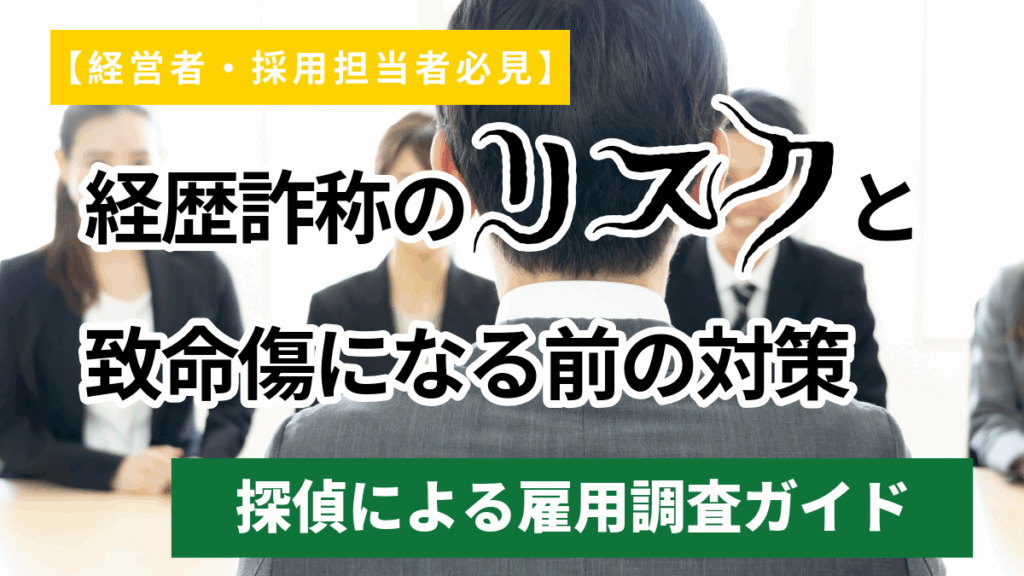 企業にとって「人材」は最大の資産であり、採用は経営戦略の中でも重要な要素です。しかし、採用活動の現場では「経歴詐称」という深刻な問題が後を絶ちません。
企業にとって「人材」は最大の資産であり、採用は経営戦略の中でも重要な要素です。しかし、採用活動の現場では「経歴詐称」という深刻な問題が後を絶ちません。
履歴書や職務経歴書に虚偽の内容を記載し、あたかも優秀な人材であるかのように装うケースは年々増加傾向にあります。
経歴詐称を見抜けずに雇用してしまった場合、多大な損害につながる可能性があります。
本記事では、経歴詐称の実態や雇用におけるリスクを解説し、最終的に 探偵事務所への調査依頼という有効なリスク回避策 についてご紹介します。
目次
経歴詐称とは?
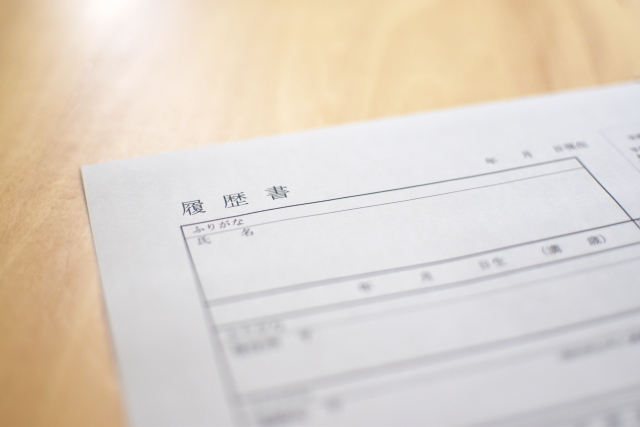 経歴詐称の定義
経歴詐称の定義
経歴詐称とは、求職者が就職や転職を有利に進めるために、自身の経歴や資格、職務経験などを偽る行為を指します。
特に「学歴」「資格」「職務経歴」「離職理由」の4つは詐称が多発する代表的な分野です。
よくある経歴詐称の例
- 学歴:大学中退を「卒業」と記載
- 資格:未取得資格を履歴書に記載
- 職歴:アルバイト経験を「正社員経験」と水増し
- 離職理由:懲戒解雇を「家庭の事情による退職」と偽る
経歴詐称が増える背景
- 競争が激しい転職市場
- 即戦力を求める企業のニーズ
- 履歴書や職務経歴書を重視する日本特有の採用文化
- SNSやネット上の情報を利用して虚偽を信じ込ませやすい環境
経歴詐称が発覚するタイミング
経歴詐称は採用直後には気づかれないケースが多く、以下の場面で露見することがあります。
- 業務スキル不足により成果が出ない
- 資格証明書や卒業証明書の提出を求められたとき
- 同業界の人脈を通じて過去の勤務先が確認されたとき
- 内部告発や同僚からの指摘
経歴詐称が発覚した時点で、企業は 雇用契約の見直し、懲戒処分、解雇、損害賠償請求 といった重大な対応を迫られることになります。
経歴詐称者を雇用するリスク
1.業務上のリスク
必要な知識やスキルを持たない人材が採用されれば、業務が停滞し、重大なミスや事故につながる危険があります。特に医療、建設、金融といった専門性の高い業界では致命的です。
2.組織への悪影響
経歴詐称が発覚した場合、同僚や上司との信頼関係は崩壊します。「なぜ企業は見抜けなかったのか」という不満が噴出し、士気の低下や離職につながります。
3.法的リスク
- 契約違反による損害賠償請求
- 顧客への説明責任
- 不正アクセスや情報漏洩につながるケースも存在
- 企業の信用失墜
一度「経歴詐称社員を雇用した企業」というレッテルが貼られると、取引先や求職者からの信頼を失う可能性があります。SNSや報道で拡散されればブランドイメージは大きく損なわれます。
実際にあった経歴詐称トラブル事例
事例1:資格詐称による医療ミス
医療機関に採用された人物が、看護師資格を偽っていたケース。採用後に実務経験不足が明らかとなり、医療ミスを起こしかけたため大きな問題となりました。
事例2:金融業界での職歴偽装
大手金融機関での勤務経験を偽って採用された社員が、実際には基本的な知識も持ち合わせておらず、重要な契約でトラブルを発生させました。その結果、取引先からの信頼を失い契約解除に至った事例もあります。
事例3:役職詐称による社内混乱
マネージャー経験を偽って採用された社員が実際にはマネジメント経験ゼロで、チーム運営が崩壊。数名の部下が短期間で退職する事態となりました。
これらの事例からも分かるように、経歴詐称は企業に甚大な被害をもたらします。
少しでも候補者に疑念を感じたら、手遅れになる前に専門家にご相談ください。
経歴詐称を防ぐために企業ができること
 書類確認を徹底
書類確認を徹底
履歴書・職務経歴書に不自然な点がないか細かく確認する。特に「空白期間」「転職回数の多さ」はチェックポイントです。
卒業証明書・資格証明書の提出を求める
学歴や資格は口頭ではなく、正式な証明書で裏付けを取ることが重要です。
リファレンスチェックの活用
前職の上司や同僚から人柄や実績を確認する方法です。ただし個人情報保護や守秘義務に配慮する必要があります。
面接で深掘り質問
経歴や業務経験について、具体的なエピソードを聞き出すことで虚偽が浮き彫りになることがあります。例えば次のような質問を投げかけてみましょう。
・職務経歴の空白期間について、具体的な理由を説明できますか?
・過去の成功体験について、あなたの具体的な役割と貢献度を数値で示せますか?
・前職の退職理由について、ネガティブな側面も含めて正直に話せますか?
・(専門職の場合)〇〇という状況で、あなたならどう判断・行動しますか?
専門調査機関への依頼
自社だけでは限界があるため、最終的なリスク回避策として探偵事務所などの第三者機関による調査を活用する企業が増えています。
探偵事務所に依頼するメリット
専門的な調査力
探偵事務所は、公開情報や聞き込み調査、必要に応じた現地確認などを通じて、応募者の経歴を徹底的に調べることが可能です。
客観的な証拠を確保
「疑わしい」ではなく「事実に基づく証拠」を得られるため、採用判断に活用できるだけでなく、トラブル発生時の法的対応にも役立ちます。
素行調査で人物像を把握
経歴だけでなく、普段の生活態度や人間関係、トラブル歴なども確認できます。これにより「採用後に問題を起こさない人物か」を事前に見極められます。
違法性のない安全な調査
企業が独自に調査しようとすると、法的リスクや個人情報の壁に阻まれますが、探偵事務所であれば適法かつ専門的に調査を行えます。
関連記事:法人調査を依頼したい!探偵はどう選ぶ?5つのチェックポイントを抑えよう!
よくある質問(FAQ)
Q1. 経歴詐称は法律違反になりますか?
経歴詐称そのものは刑事罰の対象にはなりませんが、雇用契約を結ぶ上で虚偽の申告をした場合、民事上の契約違反にあたる可能性があります。特に資格や免許を偽って就労し、業務上のトラブルを招いた場合には、損害賠償請求や懲戒解雇の対象となることがあります。
Q2. 経歴詐称はどの程度の割合で起こっているのですか?
採用調査の業界調査によれば、転職市場において数%〜一割程度の応募者が経歴に虚偽を含んでいるとも言われています。特に職歴や資格に関する虚偽は見抜きにくく、企業にとっては大きなリスク要因となっています。
Q3. 経歴詐称は入社後にバレることが多いのですか?
はい。多くの場合、入社後の業務能力不足や証明書類の提出要求、さらには同業界での口コミや人脈を通じて発覚します。経歴詐称が発覚するタイミングが遅ければ遅いほど、企業へのダメージも大きくなります。
Q4. 経歴詐称が発覚した場合、企業はどのように対応すべきですか?
まずは事実確認を行い、虚偽申告の程度を精査する必要があります。重大な詐称(資格や職務経歴の虚偽など)の場合は、懲戒解雇や損害賠償請求も検討対象となります。また、再発防止の観点から、採用プロセスの見直しも欠かせません。
Q5. 経歴詐称を防ぐために企業ができる最も効果的な方法は?
書類チェックや証明書の提出だけでなく、リファレンスチェックや第三者調査を組み合わせることが効果的です。特に疑念がある場合には、探偵事務所に依頼することで客観的かつ確実な情報を得ることができます。
Q6. 探偵事務所に調査を依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
調査内容や対象範囲によって費用は変動しますが、数万円〜十数万円程度が一般的です。経歴詐称による採用ミスがもたらす損害を考えると、事前調査のコストは十分に投資に見合うと言えます。
Q7. 個人情報保護法に抵触することはありませんか?
探偵事務所は、適法かつ正規の方法で調査を行います。違法な手段(不正アクセス、盗聴など)は一切行いませんので、企業としても安心して依頼できます。
まとめ
経歴詐称は「小さな嘘」と思われがちですが、採用後には企業に甚大な被害をもたらすリスク要因です。
- 業務遂行能力の欠如
- 信頼関係の崩壊
- 法的リスク
- 企業ブランドの失墜
これらを防ぐためには、採用時に徹底した確認作業とともに、必要に応じて探偵事務所への調査依頼を活用することが最も確実な方法です。
もし「経歴に不自然な点がある」「採用して問題が起きないか不安」と感じた際は、早めの調査が企業を守る第一歩となります。
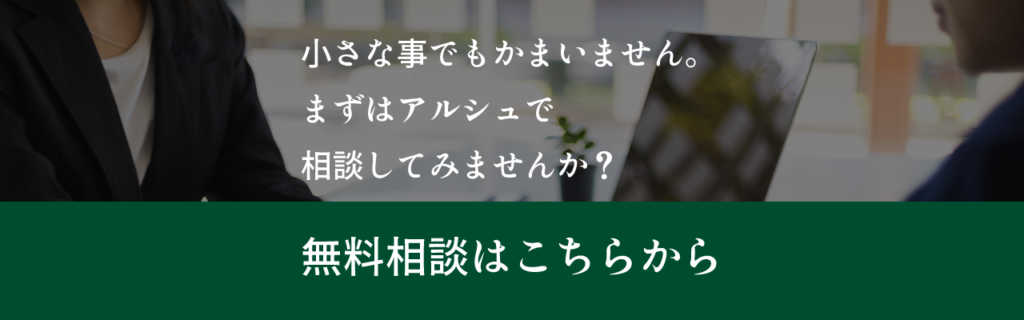 千葉県船橋市総合探偵事務所アルシュへのお問い合わせはコチラから。
千葉県船橋市総合探偵事務所アルシュへのお問い合わせはコチラから。