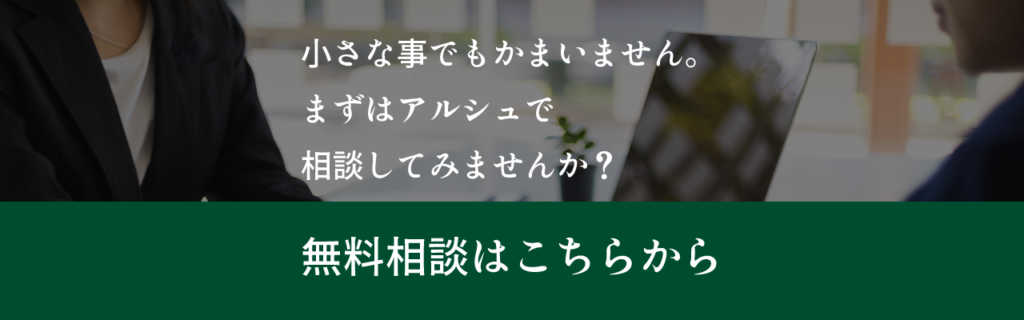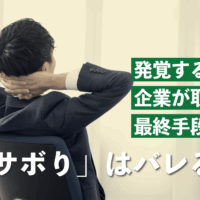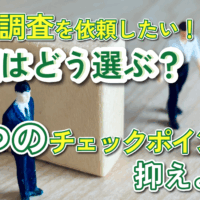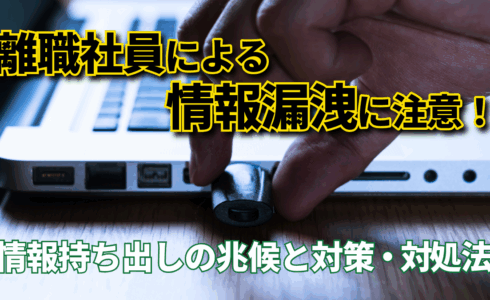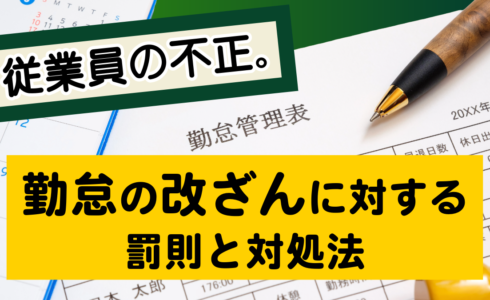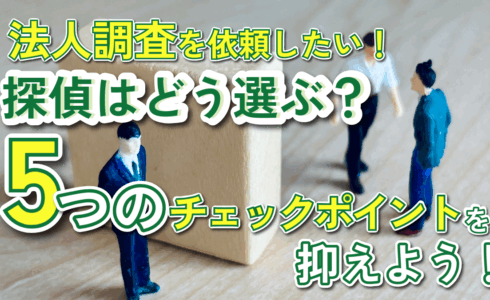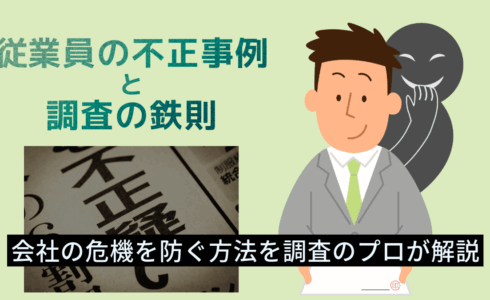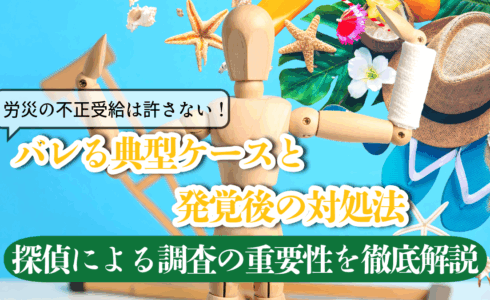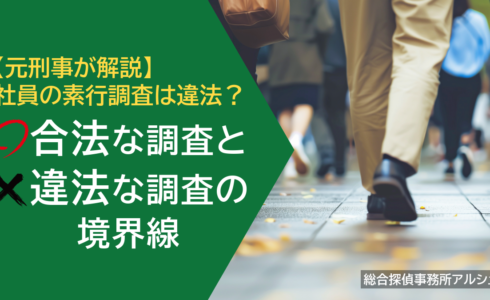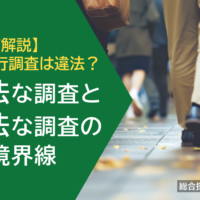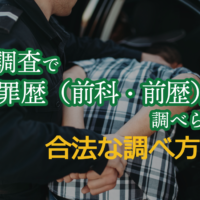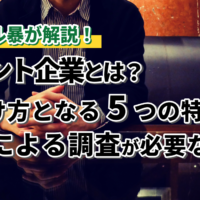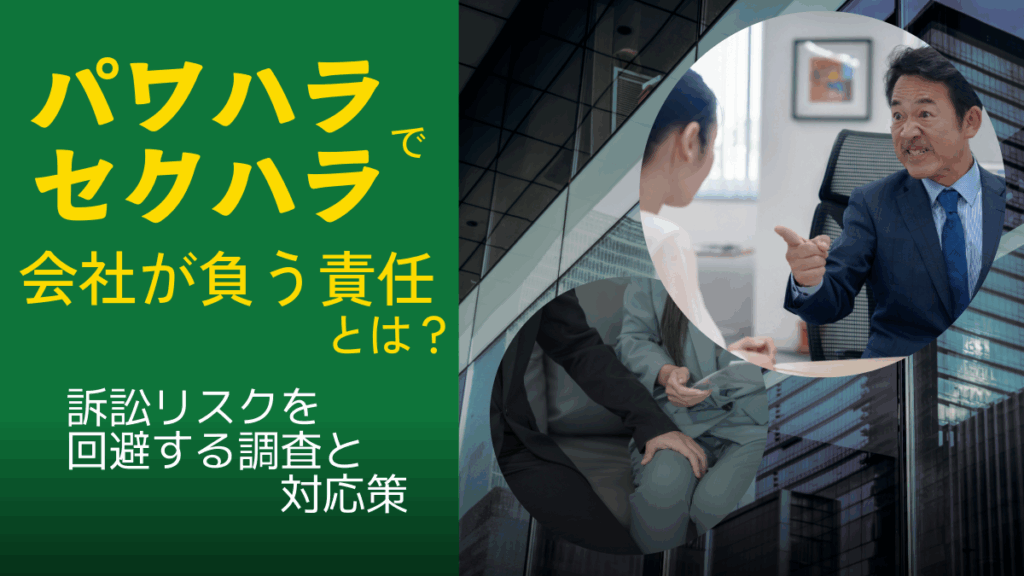 「うちの会社は大丈夫」「社員の問題は当事者で解決」そう思っていませんか?
「うちの会社は大丈夫」「社員の問題は当事者で解決」そう思っていませんか?
パワハラやセクハラは、もはや単なる「個人の問題」ではありません。
ひとたび発生すれば、被害者の心身を深く傷つけるだけでなく、優秀な人材の流出、社内の士気低下、ブランドイメージの失墜、そして何より多額の損害賠償請求へと発展する可能性もある、企業の存続をも脅かす重大な経営リスクです。
本記事では、パワハラ・セクハラ問題における会社の責任と、訴訟リスクを回避するための正しい対応、そして問題が深刻化する前に打つべき「究極の一手」について、詳しく解説していきます。
目次
そもそも「パワハラ」「セクハラ」とは?その定義と具体例

対策を講じる前に、まずは敵を知る必要があります。法律上、パワハラ・セクハラはどのように定義されているのでしょうか。
職場のパワーハラスメント(パワハラ)
職場のパワハラとは、以下の3つの要素を全て満たすものと定義されています。
- 優越的な関係を背景とした言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるもの
具体的には、以下の6つの類型が典型例として挙げられます。
- 身体的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的な攻撃:人格を否定するような暴言、脅迫、長時間にわたる叱責
- 人間関係からの切り離し:無視、隔離、仲間外れにする
- 過大な要求:到底達成不可能なノルマを課す、業務に関係ない私的な雑用を強制する
- 過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
- 個の侵害:プライベートなことに過度に立ち入る、個人情報を本人の許可なく暴露する
職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場のセクハラは、大きく2つのタイプに分けられます。
-
対価型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動に対し、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること。
-
環境型セクハラ
性的な言動により職場環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じること。
身体への不必要な接触はもちろん、「恋人はいるのか」といった執拗な質問、性的な噂の流布、ポルノ画像の掲示などもセクハラに該当します。
「知らなかった」では済まされない。企業が負う法的責任の重さ

パワハラやセクハラが発生した場合、加害者本人が責任を問われるのは当然ですが、会社もまた、極めて重い法的責任を負うことになります。これが最大のリスクです。
主に、会社は以下の2つの法的責任を問われます。
-
使用者責任(民法715条)
従業員(加害者)が、その業務を行う中で第三者(被害者)に損害を与えた場合、会社もその損害を賠償する責任を負う、というものです。
裁判所は「業務を行う中で」という部分を広く解釈する傾向にあります。たとえ休憩時間や飲み会の場であったとしても、職務との関連性が認められれば、使用者責任が問われる可能性は十分にあります。
-
安全配慮義務違反(労働契約法5条)
会社は、従業員が生命・身体等の安全を確保しつつ、健康に働けるように必要な配慮をする義務を負っています。パワハラやセクハラが横行する職場環境を放置することは、この「安全配慮義務」に違反すると判断されます。
これらの責任を根拠に、被害者から会社に対して損害賠償請求訴訟が起こされるのです。慰謝料はもちろん、精神疾患による休業中の賃金、退職に追い込まれた場合の逸失利益など、賠償額は数千万円に上るケースもあります。
会社の責任は、金銭的なものだけではありません。訴訟沙汰になれば、メディアで報道され、社会的信用は失墜します。「ハラスメントが横行するブラック企業」というレッテルは、採用活動や取引関係にも深刻なダメージを与えるようになるでしょう。
問題発生!その時、会社の対応が生死を分ける

万が一、従業員からハラスメントの相談があった場合、会社の対応次第で、その後の展開は天国と地獄ほどに変わります。
やってはいけない「NG対応」
私がこれまで見てきた中で、問題を深刻化させる典型的なNG対応は以下の通りです。
- 放置・先延ばし:「忙しいから後で」「もう少し様子を見よう」は最悪の選択です。
- 当事者間での解決を促す:「お互い様だから、うまくやってよ」と丸投げする。
- 被害者の訴えを軽視する:「考えすぎじゃない?」「あなたにも原因があるのでは?」と被害者を責める。
- 加害者の言い分を鵜呑みにする:役職が上の者や、普段の勤務態度が良い者の話を信じ込んでしまう。
- 相談したことによる不利益な取り扱い:相談者を異動させたり、「面倒な社員」とレッテルを貼ったりする。
これらの対応は、被害者の心をさらに深く傷つけ、会社への不信感を決定的なものにします。まさに、訴訟への引き金を自ら引くようなものです。
企業が取るべき「正しい対応」
では、どうすればいいのか。企業には、迅速かつ誠実な対応が求められます。
相談窓口の明確化と事実関係の迅速な調査
まずは、相談しやすい窓口を設置・周知し、相談があった際は、プライバシーに配慮しながら速やかに聞き取りを行います。
中立的な立場での調査
被害者、加害者とされる人物、そして第三者(同僚など)から、公平に事情を聴取します。決して予断を持たず、客観的な事実確認に徹することが重要です。
適切な措置の実施
事実が確認できた場合、就業規則に基づき加害者を厳正に処分します。同時に、被害者の就業環境改善やメンタルヘルスケアにも配慮します。必要であれば、両者の配置転換なども検討します。
再発防止策の徹底
ハラスメント研修の実施や、経営トップによる撲滅宣言など、全社を挙げて再発防止に取り組む姿勢を明確に示します。
社内チームだけの調査では不十分?
「正しい対応は分かった。社内で調査チームを組めばいいのだろう?」
そう思われるかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。調査の専門家である探偵として断言しますが、組織内部の人間だけで、真実を解明するのは極めて困難です。
社内調査には、以下のような限界があります。
人間関係のしがらみ
「上司に逆らえない」「同僚を売ることはできない」といった忖度が働き、関係者が本当のことを話さないケースが多々あります。
調査ノウハウの不足
誰に、何を、どのように聞くのか。矛盾する証言をどう見抜くのか。有効な証拠をどうやって確保するのか。これらは専門的な技術であり、人事担当者が一朝一夕で身につけられるものではありません。
客観性・中立性の欠如
調査担当者も同じ会社の人間です。無意識のうちに会社にとって都合の良い結論に誘導してしまったり、特定の派閥に肩入れしてしまったりするリスクを排除できません。
隠蔽・証拠隠滅のリスク
調査が開始されると、加害者やその同調者が口裏合わせをしたり、不利なメールや書類を破棄したりする可能性があります。
総合探偵事務所アルシュの探偵は刑事時代、「人の嘘」と常に向き合ってきました。人は保身のために、驚くほど巧みに嘘をつきます。その嘘を見破り、客観的な証拠を積み上げて真実を炙り出すのが、我々の仕事でした。自社チームの社内調査では、この「嘘との戦い」に勝つことは非常に難しいのです。
訴訟リスクを未然に防ぐ「予防調査」。探偵だからできること
そこで私たちが提案するのが、問題が表面化する前、あるいは初期段階で、第三者である探偵による「予防調査」をご活用いただくことです。
「探偵なんて、大げさだ」と思われるかもしれません。しかし、考えてみてください。訴訟に発展し、数千万円の賠償と失墜した信用を取り戻すコストに比べれば、プロによる調査費用は、はるかに安価な「投資」です。
私たち元刑事の探偵だからこそ提供できる価値があります。
徹底した客観性・中立性
社内の利害関係から完全に独立しているため、一切の忖度なく事実認定に集中できます。これにより、調査報告書は裁判においても極めて信頼性の高い証拠となり得ます。
プロの調査手法による確実な証拠収集
巧みな聞き込み調査で関係者から核心的な証言を引き出します。必要であれば、素行調査(行動確認)によって客観的な証拠を掴むことも可能です。「言った、言わない」「やった、やってない」の水掛け論に終止符を打ちます。
潜在的リスクの洗い出し
特定の部署で離職率が異常に高い、特定の管理職に関する不穏な噂が絶えない、といった段階でご相談いただければ、問題が深刻化する前に内偵調査を行い、リスクの芽を摘むことも可能です。これは、まさに「企業の健康診断」と言えるでしょう。
従業員の安心感
「第三者の専門機関が調査してくれる」という事実は、被害者や情報提供者に大きな安心感を与え、真実を話しやすい環境を醸成します。
刑事は事件が「起きてから」動きます。しかし、探偵は事件を「起こさせない」ためにも動けるのです。
まとめ
パワハラ・セクハラ問題は、どの企業にも潜む時限爆弾です。その導火線に火がついてからでは、もう手遅れかもしれません。
大切なのは、問題が起きない職場環境を日頃から整備すること、そして、万が一問題の兆候が見られた際には、初期段階で専門家の力を借りて、迅速かつ適切に対応することです。
見て見ぬふりをすれば、問題は必ず深刻化します。社内だけで抱え込もうとすれば、調査は難航し、さらなるトラブルを招きかねません。
総合探偵事務所アルシュは、元刑事としての経験と探偵としての調査能力を駆使し、貴社の健全な経営を守るためのパートナーとなります。
「最近、あの部署の雰囲気が悪い」「気になる社員がいるが、どう対応すべきか…」
どんな些細な懸念でも構いません。訴訟という最悪の事態を招く前に、まずは一度、私たちプロにご相談ください。秘密厳守で、貴社に最適な解決策をご提案いたします。