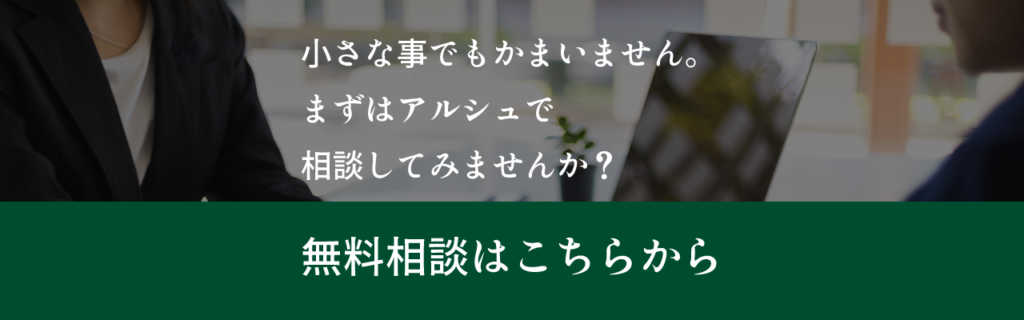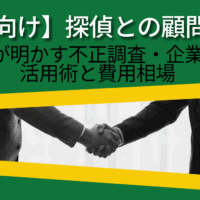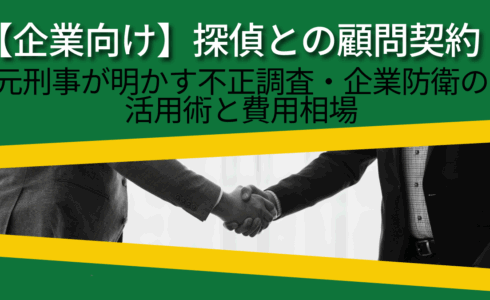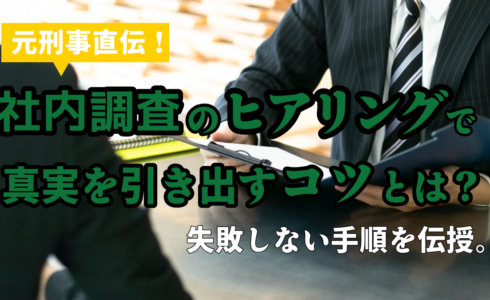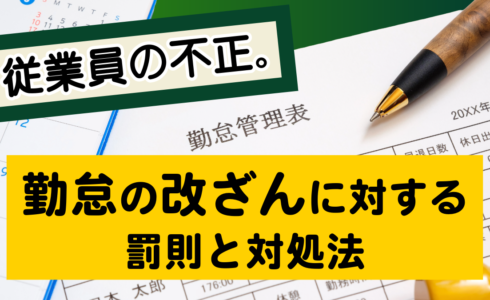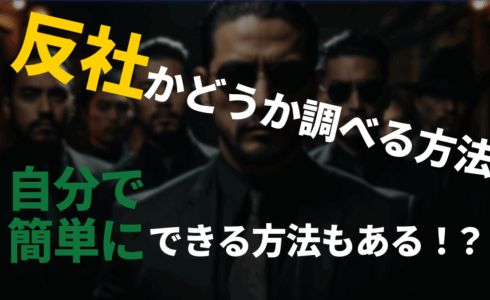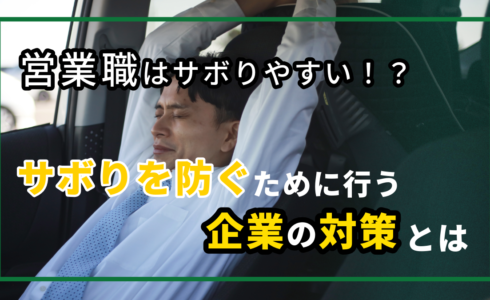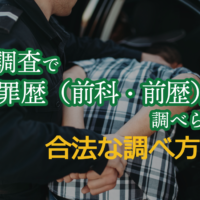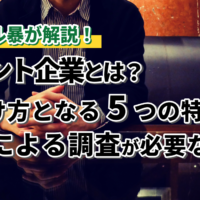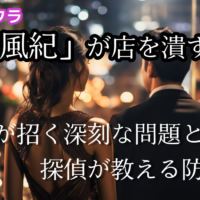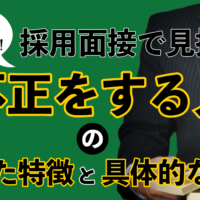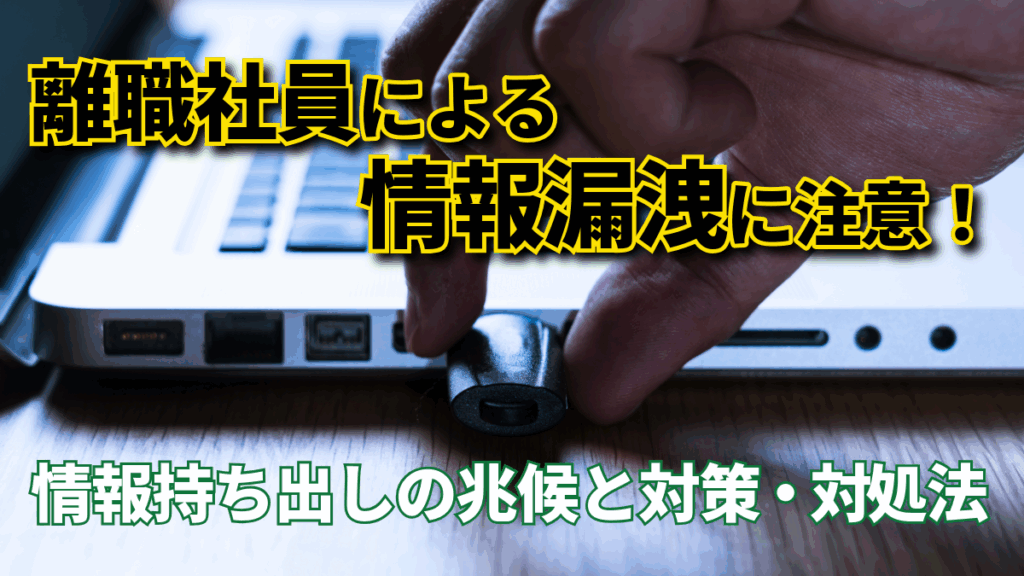
「長年貢献してくれた社員だ。円満退社だし、まさか彼が…」
企業の経営者様から、このような悲痛な声をお聞きすることがあります。信頼していた社員が退職する際に、会社の生命線ともいえる顧客リストや技術情報、営業秘密などを密かに情報持ち出ししていた――。残念ながら、これは決して他人事ではありません。
私が刑事として数々の事件を捜査してきた経験上、企業に最も深刻なダメージを与えるのは、外部からのサイバー攻撃よりも、むしろ内部、特に離職社員による情報漏洩であることが少なくないのです。
なぜなら、彼らは「元・味方」。どこに重要な情報があるのか、セキュリティの穴はどこかを知り尽くしています。一度情報が持ち出されれば、競合他社に渡り、一瞬にして企業の競争力は失われ、顧客の信頼は地に堕ちます。
この記事では、元刑事という私の経験を元に、
- なぜ離職社員は情報持ち出しに手を染めてしまうのか?その心理的背景
- 退職が近づく社員が見せる、危険な情報漏洩の兆候
- 情報持ち出しを未然に防ぐための、入社時から退職時までの具体的な対策
- 万が一、持ち出しが発覚した際の正しい対処法
これら全てを、具体的かつ実践的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの会社を「裏切り」から守るための確かな知識が身についているはずです。
目次
なぜ離職社員は情報を持ち出すのか?元刑事が分析する3つの動機

犯行には必ず動機があります。情報持ち出しという行為の裏に隠された心理を理解することは、有効な対策を講じるための第一歩です。離職社員が情報を持ち出す主な動機は、大きく3つに分類できます。
1.再就職先への「手土産」
最も多いのがこのケースです。転職先で自身の価値を高く見せ、即戦力として活躍するために、前職の顧客リストや営業ノウハウ、企画書、技術データなどを持ち出すパターンです。「これだけの情報を持ってきた自分は有能だ」とアピールしたい、あるいは転職先から暗に要求される場合もあります。これは、自身のキャリアアップのためという利己的な動機であり、計画的に行われることが多いのが特徴です。
2.会社への「復讐・報復」
解雇や左遷、あるいは在職中の待遇に対する不満や恨みが動機となるケースです。この場合、目的は金銭やキャリアではなく、会社にダメージを与えること自体にあります。そのため、情報を競合に売るだけでなく、インターネット上に暴露するなど、より悪質で破壊的な行動に出る危険性を孕んでいます。刑事事件に発展しやすいのも、このパターンです。
3.「自分の成果物」という誤った認識
意外に思われるかもしれませんが、本人に明確な悪意がないケースも存在します。「自分が苦労して作成した企画書だから」「自分が担当して築き上げた顧客リストだから」といった理由で、会社の情報を個人の所有物だと勘違いし、安易に持ち出してしまうのです。特に、個人のPCで作業することが多かったり、リモートワークが主体だったりすると、この公私の区別が曖昧になりがちです。しかし、理由はどうあれ、会社の業務として作成した情報の所有権は会社にあり、無断での持ち出しは契約違反、場合によっては法的な罪に問われる重大な行為であることに変わりはありません。
【退職前の危険信号】見逃すな!情報持ち出しの兆候

犯行前には、必ず何らかの予兆、いわば「挙動不審」な点が見られます。刑事は、こうした些細な行動の矛盾点から犯行の意図を読み解きます。退職が決まった、あるいはその気配がある社員に以下のような兆候が見られたら、最大限の注意が必要です。
システム上の兆候(データは嘘をつかない)
- 退職日直前の駆け込みダウンロード:退職日が近づくにつれ、ファイルサーバーや社内データベースから大量のデータをダウンロードしている。
- クラウドストレージへの頻繁なアクセス:個人のGoogle DriveやDropboxといったクラウドストレージへ、業務データをアップロードしている形跡がある。
- 私用メールへのデータ送信:会社のPCから、個人のメールアドレス宛に、業務ファイルが添付されたメールを送っている。
- 普段と違うデータへのアクセス:自身の業務とは直接関係のない、他部署の機密データや顧客リストなどにアクセスした履歴がある。
- 深夜・休日の不審なログイン:人目を避けるように、業務時間外にシステムへログインし、何らかの作業を行っている。
行動面の兆候(態度の変化を見逃すな)
- PC画面を隠す、作業内容を話さない:あなたが近づくと、慌ててPCの画面を切り替えたり、最近の業務内容について話すのをはぐらかしたりする。
- 急に増える残業:引き継ぎ業務とは別に、一人で黙々とPCに向かう時間が増えている場合、これはデータの整理・収集を行っている可能性があります。
- USBメモリや私物デバイスの頻繁な利用:会社のルールに反して、私物のUSBメモリやスマートフォン、外付けハードディスクなどを頻繁にPCに接続している。
- 同僚との距離:周囲とのコミュニケーションを避け、孤立している様子がある。退職を決意し、不正に手を染めようとしている人間は、罪悪感から人を避ける傾向があります。
これらの兆候は、あくまで危険信号です。しかし、複数の兆候が重なる場合は、情報持ち出しのリスクが高い状態にあると判断し、すぐに対策を講じるべきです。
情報持ち出しを未然に防ぐ!入社時から退職時までの鉄壁対策
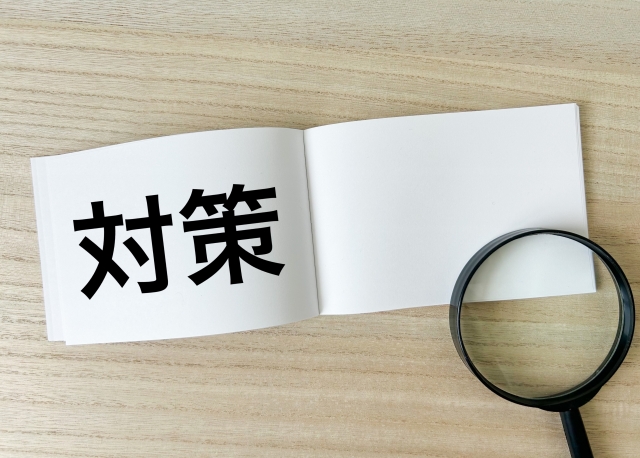
情報持ち出しは、起こってからでは手遅れです。最も重要なのは、そもそも「持ち出させない」「持ち出す気を起こさせない」環境を、組織的に構築することです。
対策は、入社時から退職時まで、一貫して行う必要があります。
入社時の対策(入口対策)
すべての基本は、従業員を迎え入れる時点にあります。
-
秘密保持誓約書(NDA)の締結
入社時に必ず署名・捺印させます。単なる手続きとしてではなく、「会社の情報にはどのようなものがあり、それを漏洩させた場合にどのような罰食があるか」を具体的に、かつ丁寧に説明し、重要性を認識させることが不可欠です。
-
情報セキュリティ研修の徹底
「会社の業務で得た情報、作成したデータは、すべて会社の資産である」という基本原則を、入社時に徹底的に教育します。
在職中の対策(環境対策)
不正が起こりにくい仕組みと文化を醸成します。
アクセス権限の最小化
従業員には、業務上必要な情報のみにアクセス権限を与える「最小権限の原則」を徹底します。役職や部署が変われば、権限も速やかに見直します。
ログ監視体制の構築
誰が、いつ、どの情報にアクセスしたのかを記録・監視するシステムを導入します。「常に見られている」という意識が、不正の強力な抑止力となります。
物理的・技術的な持ち出し制限
USBメモリなどの外部記憶媒体の使用を原則禁止、あるいは許可制にします。また、個人メールやクラウドストレージへのファイル送信を技術的にブロックするDLP(情報漏洩対策)ツールの導入も極めて有効です。
良好な職場環境
不満は不正の温床です。日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、不満が溜まりにくい風通しの良い組織文化を育むことは、最も本質的なセキュリティ対策と言えるでしょう。
退職時の対策(出口対策)
最もリスクが高まる「出口」を、厳格に管理します。
退職者向け誓約書の再取得
退職日にも、改めて秘密保持義務が退職後も継続することを確認させ、誓約書を取得します。
貸与機器の返却とデータ確認
PC、スマートフォン、社員証など、会社からの貸与物はすべて退職日までに返却させます。特にPCは、返却前にアクセスログや外部へのデータ送信履歴を専門家が調査するプロセスを設けることを強く推奨します。
アカウントの即時抹消
退職日をもって、社内システム、メール、クラウドサービスなど、すべての業務アカウントを即時に停止・削除します。最終出社日から退職日まで期間が空く場合でも、最終出社日にアカウントを停止するのが鉄則です。
万が一、持ち出しが発覚したら?元刑事が教える正しい初動対処
対策を講じても、情報持ち出しの疑いが生じてしまうこともあります。
その際の対処を誤れば、証拠を失い、泣き寝入りするしかなくなります。事件捜査と同じく、初動が全てを決定します。
ステップ1:【最優先】証拠保全
まず、対象者のPCやスマートフォンには絶対に触らないでください。電源を入れるだけでも、ログが上書きされ、決定的な証拠が消えてしまう危険があります。ネットワークから切り離し、現状のまま保全することが鉄則です。
ステップ2:客観的な事実確認
保全した機器を、私たちのような調査のプロやデジタル・フォレンジックの専門家に引き渡し、ログを解析します。「いつ、どのファイルが、どの外部媒体や宛先にコピー・送信されたか」という動かぬ証拠を掴みます。
ステップ3:本人へのヒアリング
感情的に問い詰めるのは逆効果です。ステップ2で得られた客観的な証拠を元に、「〇月〇日の〇時〇分、このファイルをUSBメモリにコピーしていますが、これは何のためですか?」というように、冷静に、しかし具体的に事実確認を行います。これは、刑事の取り調べの基本でもあります。
ステップ4:法的措置の検討
事実関係が確定したら、弁護士と相談の上、以下の措置を検討します。
- 内容証明郵便による情報の返還・破棄要求
- 不正競争防止法違反、窃盗、横領などを根拠とした刑事告訴
- 会社が被った損害に対する民事での損害賠償請求
臆することなく、毅然とした対応をとることが、将来の同様の不正を防ぐことに繋がります。
まとめ
離職社員による情報持ち出しは、企業にとって致命傷になりかねない、非常に深刻な経営リスクです。しかし、その多くは適切な対策を講じることで防ぐことができます。
その基本は、「性悪説」に立って情報持ち出しができない・しにくい仕組み(システム)を構築すること。そして同時に、従業員との信頼関係を築き、不満から不正に走らせない環境(企業文化)を育むこと。この両輪が不可欠です。
- 退職時の手続き
- 社員の不審な動き
- 情報管理体制の甘さ。
もし、少しでも心当たりや不安があれば、決して放置しないでください。問題が表面化する前に、私たちのような専門家にご相談いただくことが、あなたの会社と真面目に働く他の従業員たちの未来を守るための、最も確実な一歩となります。
総合探偵事務所アルシュ船橋へのお問い合わせはコチラから!